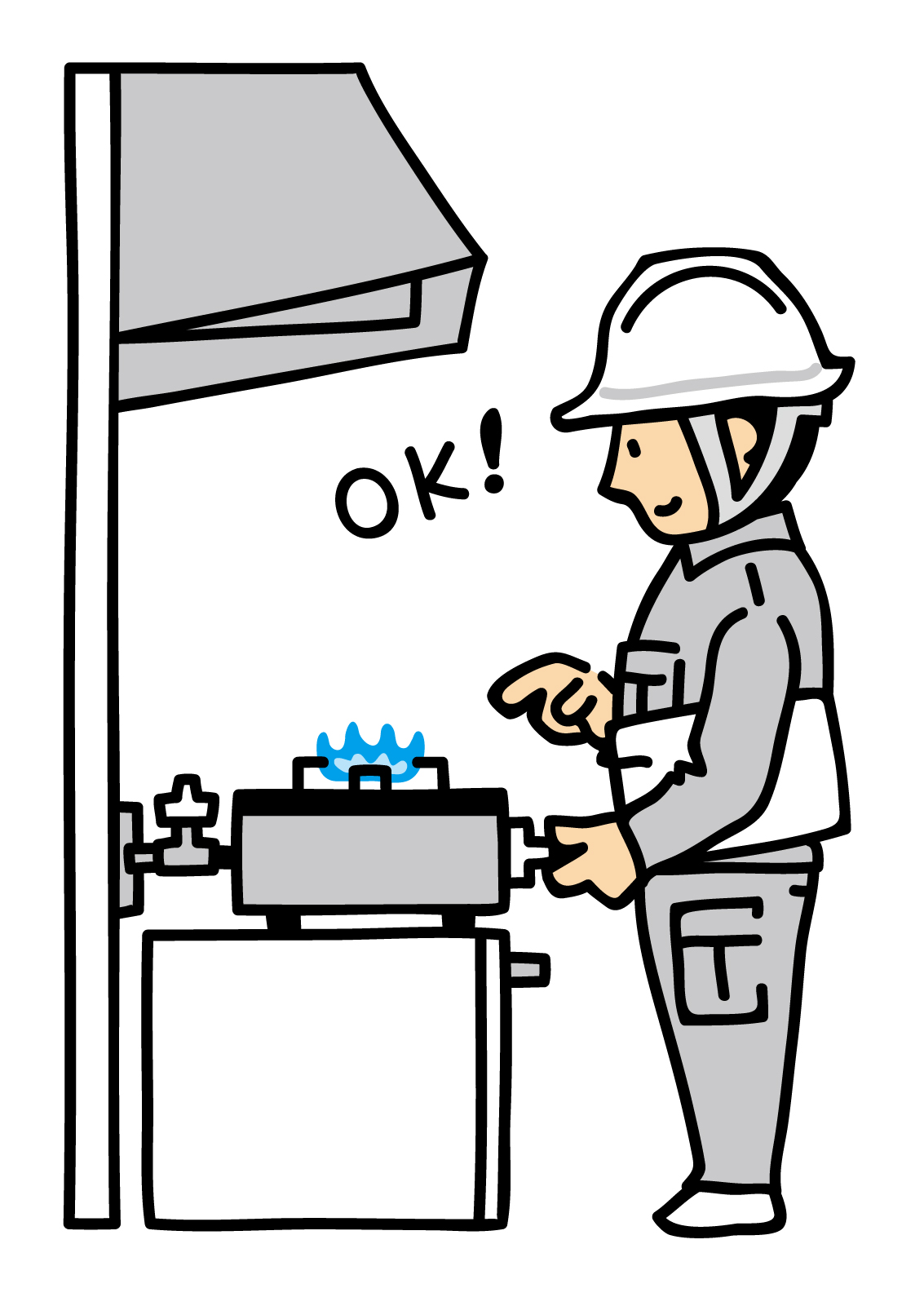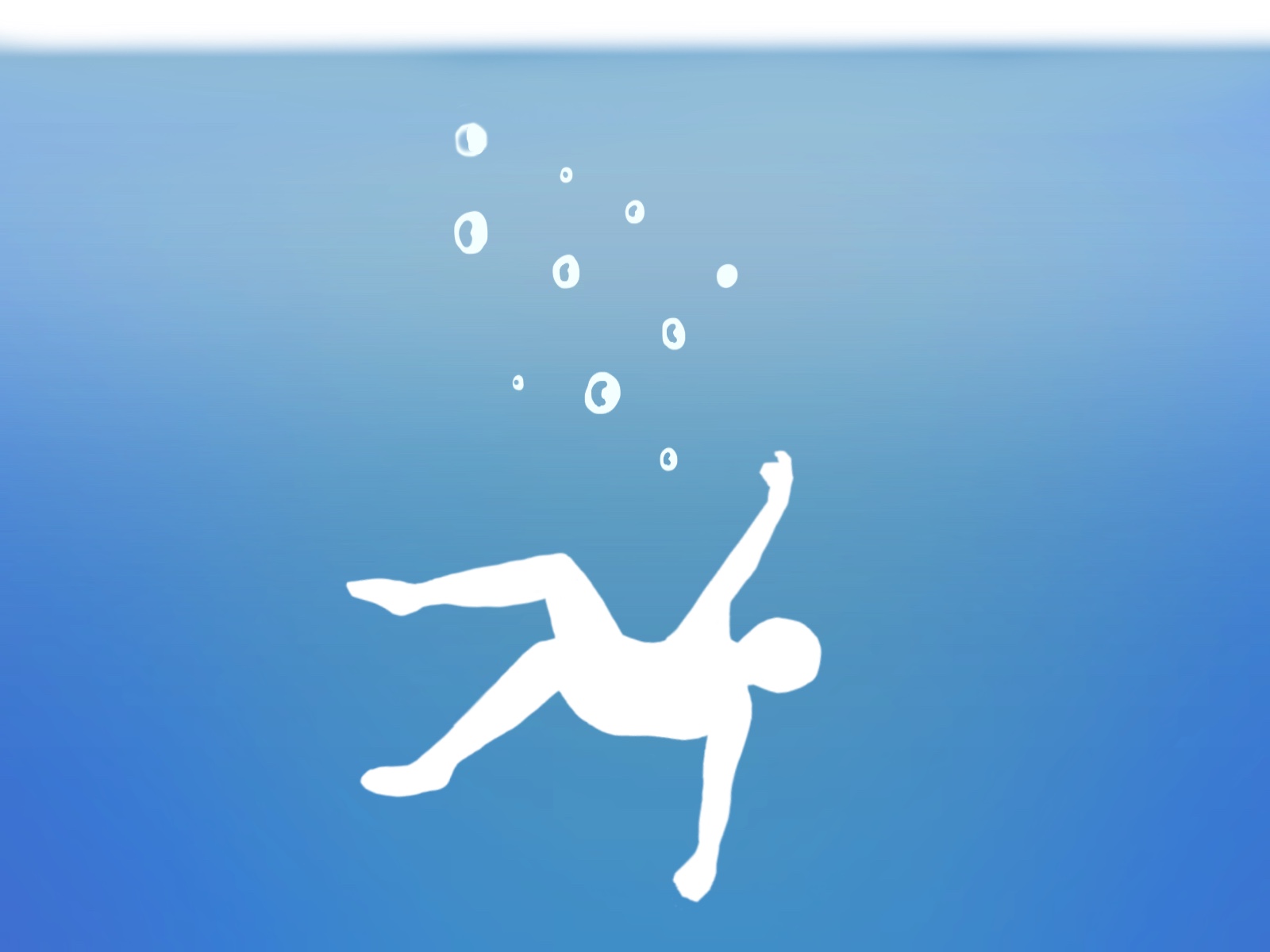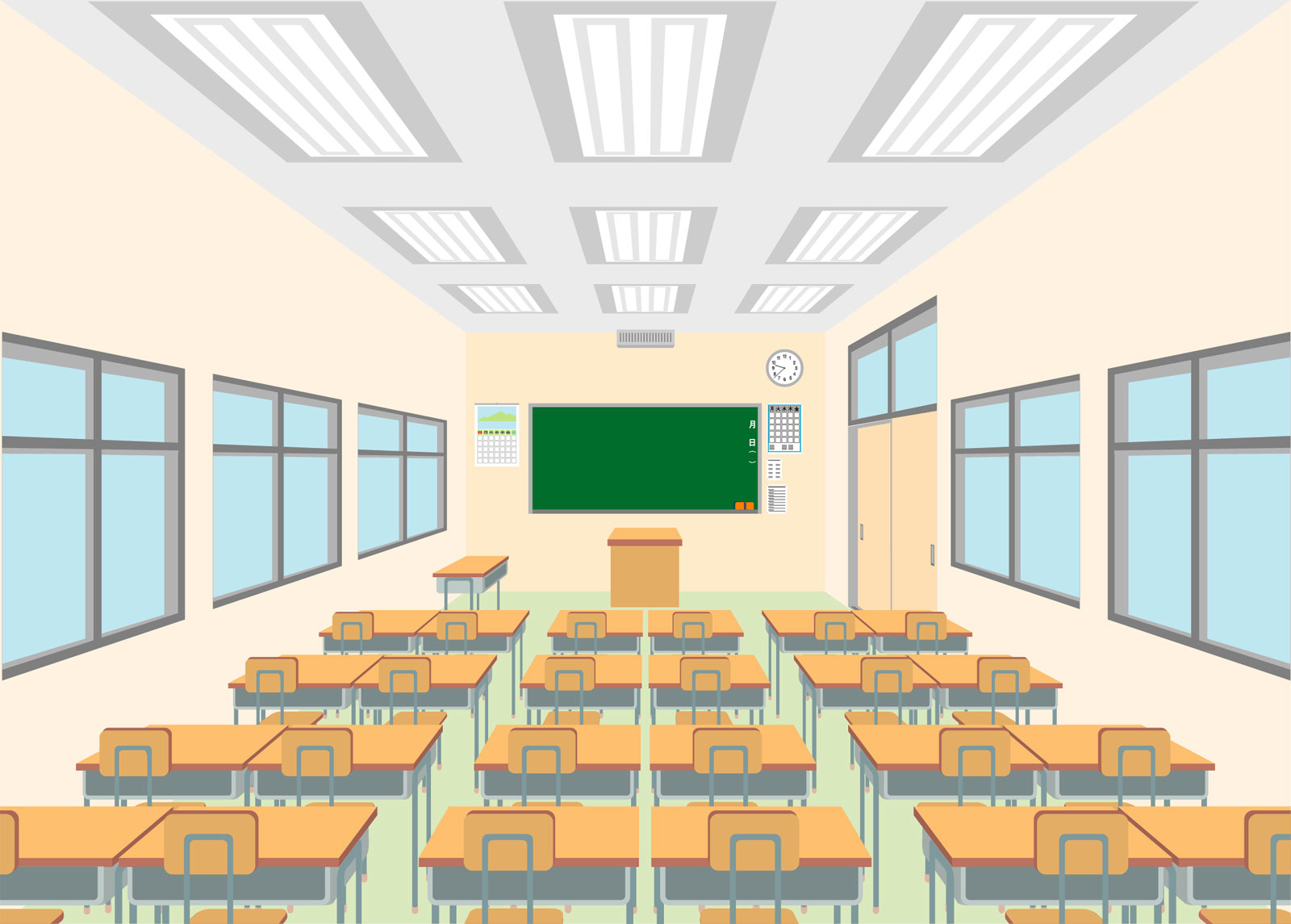溺れる者は藁をも掴む
という諺があります。
溺おぼれる者ものは藁わらをも摑つかむ
(「溺れそうになっている人は、麦藁のように頼りないものであっても、永らえようとして頼ってしまうものである」ということから)危急の時にあっては、普段なら取り合わないような、頼りないものにでさえ、助けを求めてしまうものであるということの例え、または、そのようなものにまで、助けを求めてしまうような危急の状態にあること。
引用:ウィクショナリー
このことわざを見た時に
多くの人が思い描くのが
溺れる状態でわらを掴んでしまう
人間の愚かさや
人間という存在の弱さ
これを問題視して
自分は溺れるようなことがあっても
藁をつかむ という愚行はしない
もっとしっかりしたものを掴む
または藁を つかむくらいなら
潔く無手で水を掻くと
とにかく藁のような頼りないものは
つかんじゃダメ 愚かなので
という風な認識を
してしまいがち……!

だし 私もそう思ってたンですけど
実際 このことわざの 教訓
というものを自分なりに考えてみたが
それは
溺れないこと なんですよね
溺れた後にどうするか
藁をつかむような愚かな判断をしない
ようにする……
と、そういうことではなく
ぶっちゃけ 溺れてしまったら
もう人間みんな同じなので
私も藁を掴むと思うし
それこそ明哲な人だって
藁をつかむでしょう
なんせ、溺れている状態ですから
想像を絶する苦痛の最中にいるし
またまともに 思考はできないし
数秒先は意識がなく
その先にあるのは絶命ですから

このような状態で掴むものを
的確に判断するという行為自体が
人間にはできないと考えます
なので溺れるような状態になってしまえば
もう終わりなんですよね
だから 溺れるような状態になった後に
どういう判断をするか?
というのではなく
そもそも 溺れないようにする
これが肝要
溺れる者は藁をもつかむ
という人間の弱い 性(さが)を
ことわざ が教えてくれているのだから
そういった
前後不覚な状態に置かれないようにする
ということが
この ことわざの 真の教訓
なんではないかと
思いました。